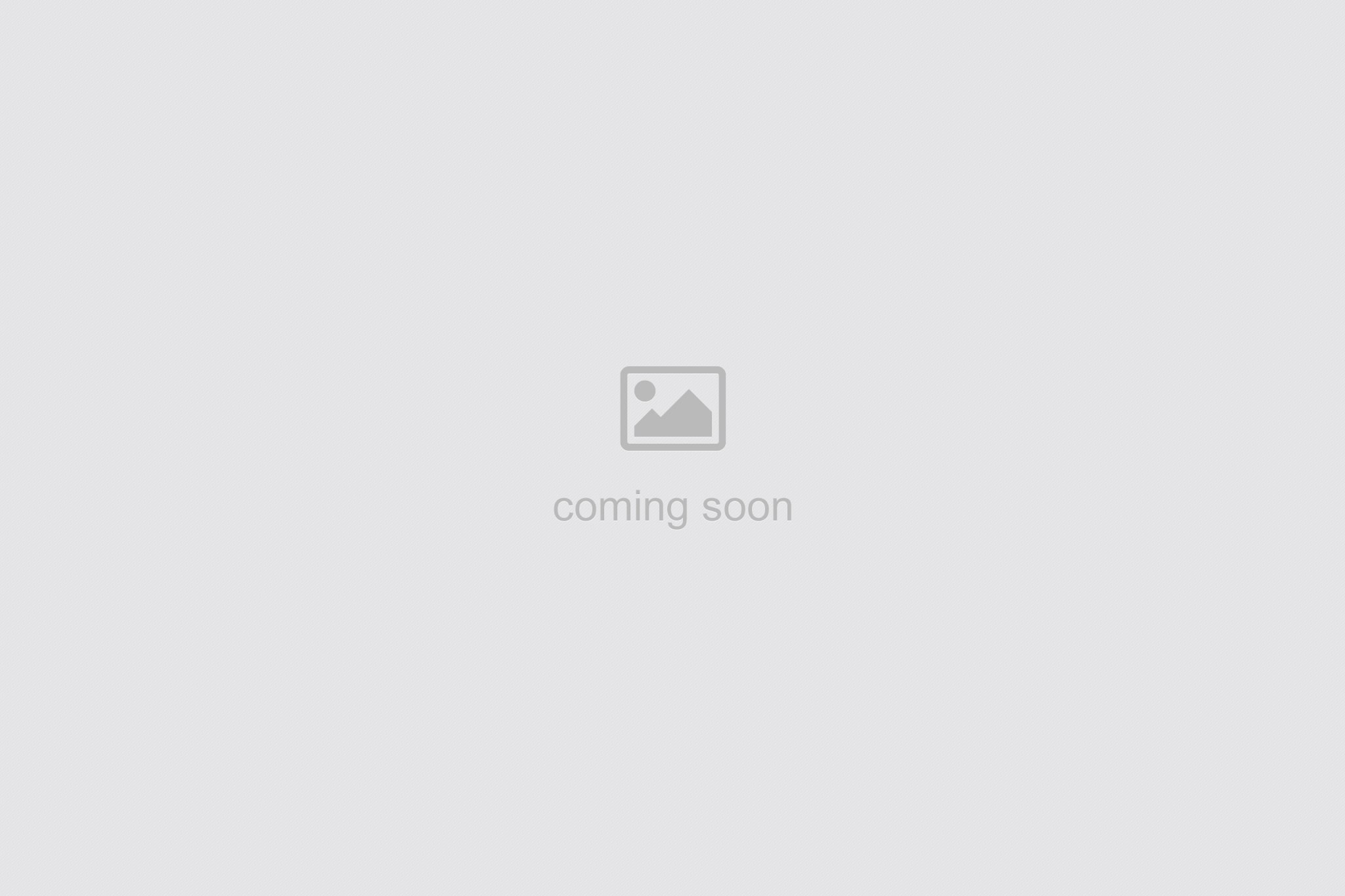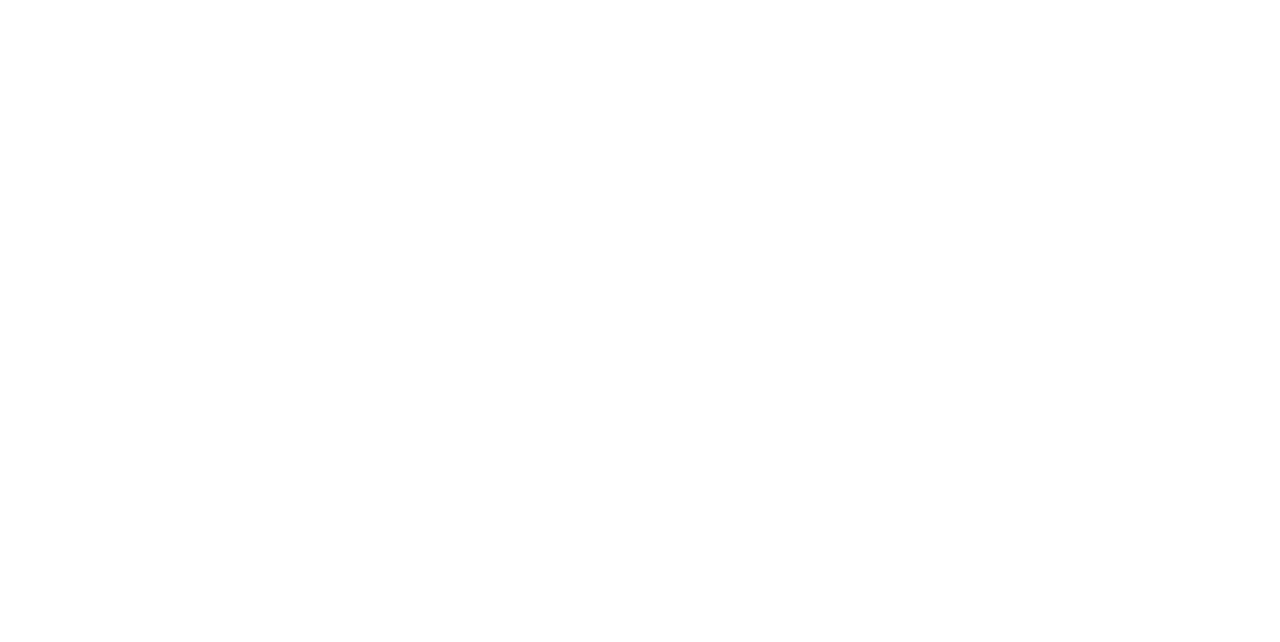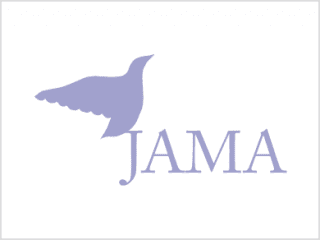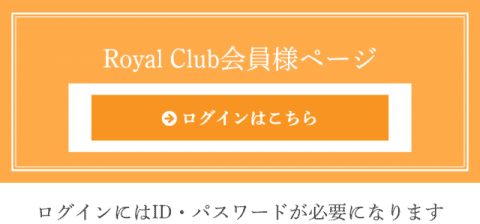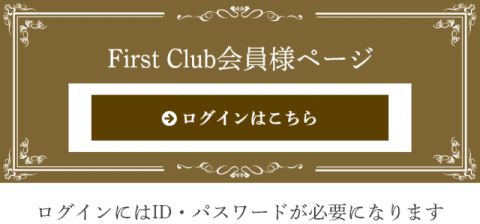ご相談について
【MA相談/プレクリニックのご予約】からだの心配を速やかに解消しましょう!
セミナーのご案内
【JAMAセミナーのご予約】生活上で病気を予防するポイントが分かります!
安全なサプリメントをお探しのかたへ
Do you have such a problem?
こんなお悩みありませんか?
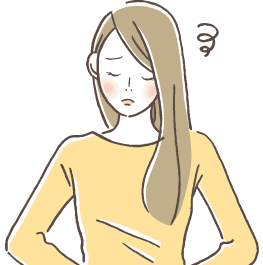
ストレス
肌トラブル
更年期の症状
栄養不足の懸念
胃腸の不調
主治医がいない
物忘れ
体力の低下
老親の健康サポート
介護のお悩み
Illness consultation
病気のご相談
がん、アトピー性皮膚炎等の疾患で、より良い新しい治療法をお探しのかた
治療中に大切な栄養補給、良質な睡眠のとりかたなどのアドバイス
不定愁訴で適切な治療をお探しのかた
首こり
強い疲労感 等